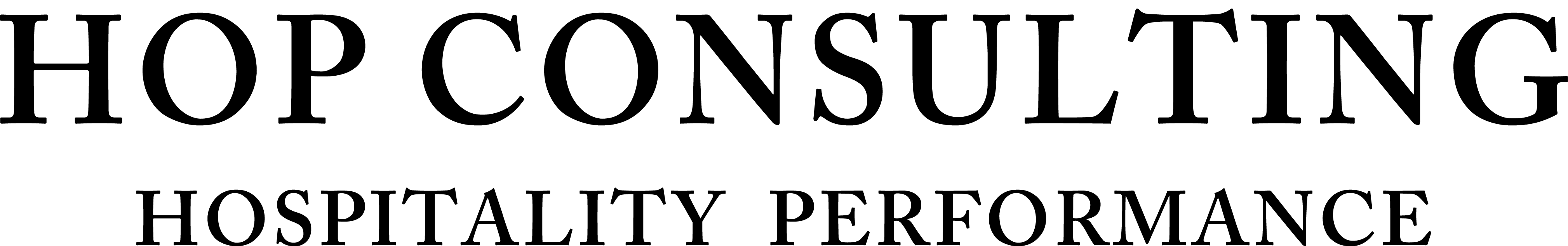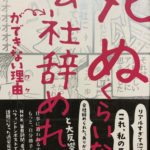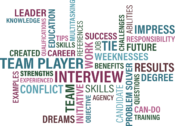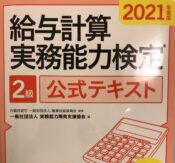就職や仕事を「好きなこと、やりたいこと」で選ばなくても案外大丈夫な理由-悩める就活生へ

最近は「好きなこと、やりたいことを仕事にすべき」という風潮が強いようで、そうした書籍や著名人の言葉などもよく見かけます。
さて、本当に好きなこと、やりたいことを基準に会社(仕事)を選ぶべきなのでしょうか?今回はこれをテーマにして考えてみたいと思います。
「好きなこと、やりたいこと」を仕事に選ばなくても案外大丈夫な理由
就職や仕事で「好きなこと・やりたいこと」選びに拘らなくても大丈夫な理由と注意すべき点
自分に合った企業や仕事を選ばないと幸せになれないのか
アドラー心理学の一つに「運命の人はいない」という考え方があります。簡単に言えば、本当は周りにいくらでも運命の人になりうる人がいるのに、自らに「勇気がない」故に、その可能性を潰してしまっているというものです。
(それこそ、道端で出会った方にアプローチしても良い訳ですから…)
「自分の好きなことではない」
「自分のやりたい仕事じゃない」
色々と理由をつけて拒むことは可能ですが、あなたの天職が何なのかは、案外あなた自身にも分かっていないものです。
例えば、あなたがこれまで生きてきた中で、将来やってみたいと思った職業は何ですか?
考えや年齢が変わるにつれ、刻々と変化して行ったのではないですか?
例えば、女の子は小さい時に「ケーキ屋さん」という将来の夢を持ちますが、実際に「ケーキ屋さん=パティシエ」になっている方は男性の方が多いなんて話を聞きます。
私は、割と日々流されるような生き方だったので、あまり夢がどうとか考えるタイプではなかったですが、自分が覚えている範囲では、漫画家や弁護士、最近だとパン屋を夢に抱いたものです。
小学校の文集などに書いたのは「漫画家」や「弁護士」です。面白さや笑いがある漫画家、かたや真面目な弁護士、お互いにどこにも共通点なさそうです(笑)。
ちなみにパン屋はただパンが好きって理由だけなので、プライベートでパンの勉強でもしようかなと考えているぐらい軽いものです。
さて、本題ですが一昔前の団塊の世代などは、集団就職と呼ばれるような形での就職が多かったと聞いています。
当時は情報網も発達していないので、当然社内の雰囲気や自分がどんな仕事をするのかも、あまり分かっていない状態だったと思います。
悪く言えば、「とりあえず就職する」「とりあえず働きに出る」といった感覚に近かったのではないでしょうか。
ですが、そうした就職であったとしても、その方々の過去や現在が「不幸なのか」と言えばそうではないと思います。
中にはやりがいのある仕事もあったでしょうし、達成感のある仕事もあったと思います。また、当時は今ほど労働基準法や労働条件が厳しい時代ではなかったですから、想像できないほど辛かったり、きつい思いを経験されたこともあると思います(パワハラやセクハラも同様です)。
(当然ながら、時代が時代だったから違法な労働条件やパワハラセクハラが許される訳ではありませんが…)
そうしたことがあってもなお、ご本人なりの「幸せ」を掴んで過ごしている方が大多数なのではないかと思います。案外、「とりあえず就職してみる」ぐらいの感覚で社会人生活をスタートしても良いのかもしれません。
好きな仕事=楽しいことばかりでもない
「仕事の8割は雑務」という言葉通り、仮に自分が好きなことを仕事にできたとしても、自分がやりたくない業務もやらなければなりません。
むしろ新入社員の頃は、自分のやりたい仕事を任せられることはほとんどないでしょう。上司や先輩から頼まれた仕事をしなければならないですし、そのような類の仕事であっても出来が悪かったりミスがあれば、当然叱責されます。
ですが、この仕事(上司や先輩から任された仕事)は自分のやりたいことじゃないからミスした、やる気が出なかった等の言い訳は通用しないものです。
仕事のすべてが夢や希望に溢れたものばかりではないこともきちんと理解しておかなければ、「せっかく入社したのに、なんか思っていたのと違う」と思って辞めてしまう可能性もあります。「好きなこと、やりたいこと」を仕事に出来たからといって、一切の苦がない訳でもないことを忘れてはいけません。
好きな仕事=他の仕事より頑張れて無理が出来る訳でもない
以前、「『死ぬくらいなら会社辞めれば』ができない理由」という本を紹介しましたが、その著書の中に、自分に無理を強いてしまう理由の一つに「好きな仕事をやっているから」ということを挙げていました。
具体的には、仕事がしんどくて苦しかったとしても「自分の好きなことをやっているんだから」「自分が選んだ道だから」「自分がやりたいと思ったことをやれているんだから」といった感情に支配されてしまい無理をしてしまうというものです。
「好きなこと・やりたいこと」を仕事に出来ているが故に、知らず知らずのうちに自らの逃げ道を塞いでしまう可能性もあることを覚えておきたいものです。
一方で最近は、自分の好きなことややりたいことはむしろ仕事ではなくプライベートで満喫(或いは副業)したいという方もいらっしゃいます。
仕事にしてしまうと、かえって余計な柵に悩まされ、楽しくないという考えです。
つまり、ある程度自己成長を感じられる仕事であれば良いと割り切って働くという方法です。企業側からすれば、そうした方々は自分の成長よりも、生活のために働くという意識が高く、仕事中のやる気・熱意といったものは見えにくいかもしれませんが、こうした方を上手くコントロールするのもこれからの経営の在り方だと思います。
流石にこの場合は、組織ではなく個人という単位での活動となるので、規模の大きなことを為すのは難しいかもしれませんが、SNSなどを通じたコラボレーション企画やクラウドファンディングなどを上手く活用すれば、組織でやるのと同等規模かそれ以上のことをするのも可能になるかもしれません。
そもそも好きなこと、やりたいことが見つからない可能性も…
「同調圧力」という言葉は嫌いなのですが、世間的に「自分のやりたいことを仕事にすべきだ」という論調が強くなれば、逆に「自分のやりたいこと、好きなことが分からない」と悩む方、或いは「好きなことを仕事にしていない自分はダメなのか」と否定的に捉える方も出てきそうなものです。
几帳面、神経質、完璧主義者…性格によっては「自分の好きなこと、やりたいこと」を探し出すこと自体が重いプレッシャーとなりかねません。周りと比べたがるのが人間の性ですから、「好きなことを仕事にしている人」が自分より輝いて見えたりするかもしれません。
こうした傾向のある方は「好きなこと、やりたいこと」にこだわりすぎて足を踏み出せない可能性もあります。もっと単純な理由や動機で踏み出してしまっても良いように思います。
最短だけが全てではない。遠回りでも学べることや見えてくるものもある
中には、希望する企業に就職出来ないケースもあると思います。
「興味が全くない訳ではないけど、第一志望ではない」。中には「行きたくはないけど、そこしか内定が出なかった」というケースもあるでしょう。
そんな時に、諦めずに四方八方手を尽くすのも、ある意味大事だと思いますが、気乗りしない企業であっても、試しに就職してみるのも一つの手だと思います。
やってみると意外と面白かったり、性に合っていたりすることもあるからです。
そこから、自分の進みたい道が見えてくることもあります。
私自身も同じような経験はありますし、興が乗って思いの外、集中してしまったこともしばしばです。
また、採用、教育がしっかりしている会社であれば、他の企業に就職した方よりも早く成長し、新人が出来ないような大きな仕事を任せられることもあります。実際、新入社員ともなれば、仕事以外の部分を鍛える必要が大いにあります。
所謂「社会人のマナー」というものです。
挨拶に始まり、名刺の受け渡し、コミュニケーション能力、PCやMicrosoftOfficeの使い方、文章力、果ては会計力、英語力などです。「仕事」を効率的に行うためには、直接的にも間接的にも必要となってくる能力です。
つまり、「好きなこと・やりたいこと」をやる前にその土台となるものも鍛える必要もある訳です。希望のところに就職出来ずその場に留まるよりも、どこかの企業に就職し基礎的なスキルを身に付けるだけでも、将来に向かって進む事になると思います。
もちろん、どうみても「ブラック企業」のような会社に無理に入社する必要はないですが、アルバイトやパートではなく、ある程度責任負って働くことは自身の成長につながるということは間違いないと思います。
望んだ場所とは違うので気乗りしない部分もあるかもしれませんが、社会人として一歩踏み出すことも大切ではないでしょうか。
今 僕のいる場所が 探してたのと違っても
引用:Mr.Children「Any」より
間違いじゃない きっと答えは一つじゃない
何度も手を加えた 汚れた自画像にほら
また12色の心で 好きな背景を描き足して行く
今は転職もしやすい。やりたいことが見つかれば別の道へ
皆さんも、「転職サイト」「Uターン・Iターン」「転職エージェント」といった言葉を耳にしたことがあると思います。
それだけ、「転職」という言葉は身近になったと言えます。
一昔前は、日本の経済成長も相まって終身雇用が当たり前の世の中でしたが、情報化社会の後押しもあり、経済情勢は一刻一刻と変わり経営も難しくなっています。実際、企業の平均寿命は24年ほどです(倒産した企業の平均)。
折角、「好きなこと・やりたいこと」が出来る企業に就職できたとしても、自分が定年(概ね43年)するまで会社が存続しているかどうかも分かりません。とりあえず、「一度入社してみて合わないなら転職を考える」という選択肢も若い世代なら当然ありだと思います。
おまけ:就活生におすすめの一冊
上記関連記事の中でも紹介していますが、就活生におすすめの一冊。
自分の内面に目を向けることや就職先の選び方・良し悪しの判断の仕方などが書かれています。
 | 苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」 [ 森岡 毅 ] 価格:1,650円 |
まとめ
情報化社会にともない、我々には沢山の選択肢と比較対象を得ることが出来る様になりましたが、そうした数ある中から、何か一つを決めるということは案外難しいものです。
例えば、自動車、パソコン、スマートフォン。色んなサイズや種類、スペックの商品が並んでおり、どれか一つに絞り込む迄にかなりの時間を費やすことになりますし、人によっては決めきれずに途中で考えるのをやめてしまったという方もいるのではないでしょうか?
こうしたことを考えると、昔と比べて便利になった分、現代人は「決断」が下手になったように思います。「決断」は責任や覚悟といった言葉に置き換えても良いのかもしれません。
だからこそ、同調圧力に代表されるように、みんな(大衆)の意見に合わせようとする傾向がある訳です。そうした方が自分で考えずに済み楽ですし、仮にその判断が間違っていても他人のせいに出来ます。
しかし、「企業への就職」という段階になると、流石に自分の人生に直結することなので、ある程度は「自分の意思」で決めなければならなくなります。
(「ある程度」としたのは、まだまだ有名企業・大企業、流行りの業界、同級生の誰々が行くから、親が勧めるから、といった理由で選ぶ方も多いからです)
団塊の世代の頃の集団就職などは、情報がないからこそ選択しやすく足を踏み出しやすかったかった訳ですが(ex.とりあえず上京して仕事を探す)、今はそう簡単にはいきません。
企業のHPに始まり、会社説明会、OB・OG訪問、退職者の口コミ(レビュー)なんてものもあり、調べよう、比較しよう、と思えば幾らでも可能になっています。
そんな中で、最もらしい「好きなこと・やりたいこと」を仕事に選ぶというルールを用いることになるのだと思いますが、これにこだわりすぎてもあまり良くないというのは先に述べた通りです。
「好きなこと・やりたいこと」を仕事にするという方針が悪いとは言いませんが、それにこだわりすぎず、ましてや好きなことを仕事にできない自分を卑下したりすることのないようにして欲しいものです。
少なくとも「〜でなければならない」という思い込みはやめて、気楽に考えるべきでしょう。「就職は人生のゴールではない。一つの選択の結果に過ぎない」といった言葉もあります。
ですから、希望した企業や職種ではなくとも、仕事をこなしていくうちに見えてくるものもありますし、場合によっては興味のある分野へ転職しても良い訳ですから(職業選択の自由)。
企業側からすれば、「そんなすぐに辞められては困る」という考え方もあると思いますが、「転職」が当たり前になるということは、労働者の流動化が進んでいるとも言えます。企業側にも、給与、福利厚生といった待遇面や魅力ある職場作りといった社員の定着率を高める努力がこの先ますます必要になってくるという訳です。
・1 自分に合った企業や仕事を選ばないと幸せになれないのか。
→団塊の世代などは好きなことを仕事にするというより、「とりあえず働かなきゃ」といった動機が多数だったと思うが、それでも幸せな方が多いのではないか。
・2 好きな仕事=楽しいことばかりでもない。
→仕事の8割は雑務。やりたいことばかりできる訳でもない。
・3 好きなこと=他の仕事より頑張れて無理が出来る訳でもない。
→好きなことを仕事にしているからといって長時間労働など無理ができる訳でもない。
・4 そもそも好きなこと、やりたいことが見つからない可能性も…
→好きなことが仕事にできなくても、或いは好きなことが見つからなくても、それはそれでOK。
・5 最短だけが全てではない。遠回りでも学べることや見えてくるものもある
→好きなこと、やりたいことをする上でも、とりあえず会社に入ってどんな業界でも必要となる基礎スキルやビジネスマナーを覚えておいて損はない。
・6 今は転職もしやすい
→転職も当たり前の世の中になってきた。とりあえず働いてみて興味が出てきた業界や分野に転職するのもあり
・7 おまけ:就活生におすすめの一冊
→「苦しかったときの話をしようか/著:森岡毅」