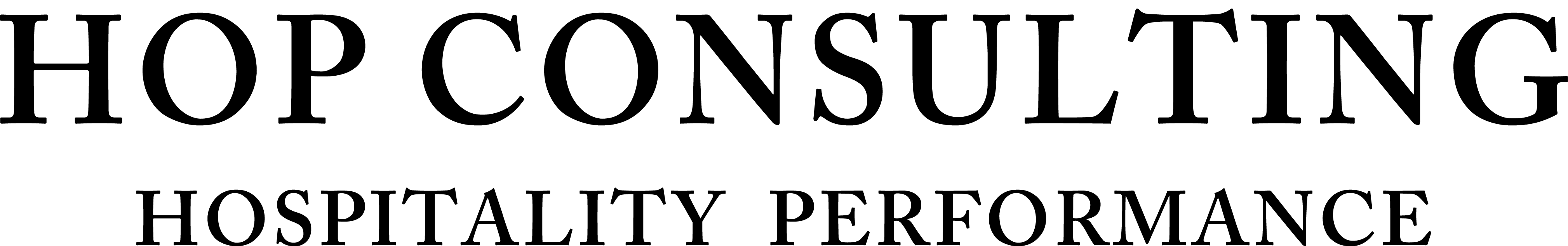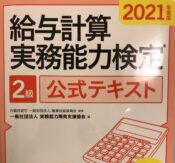【30日前の解雇予告・30日分の解雇予告手当・不当解雇】解雇予告や手当を支払えば解雇が有効となる訳ではない

「辞めさせたい社員(従業員)への対応。退職勧奨(肩たたき)の可否とポイント」で「退職」に関して少し触れました。
その際、少し言及していた「解雇予告の上での解雇」について紹介したいと思います。
「30日前の解雇予告」か「30日分の解雇予告手当の支払い」が一人歩きしている
解雇予告や解雇予告手当を支払えば、(自動的に)従業員を解雇出来ると思っている経営者の方も多いです。
法律を齧っているのは悪いことではないですが、どうも30日前や30日分といった言葉が一人歩きして、変な誤解が生じているようです。中には「1ヶ月分の給料を払えば解雇しても良い」(1ヶ月分の給与=30日分の解雇予告手当)なんて思っている経営者もいらっしゃるのではないでしょうか?
解雇の予告については、労働基準法第20条に以下のように定められています。
労働基準法第20条(解雇の予告)
/引用:労働基準法
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
この条文(特に太字部分)にある「少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならない」もしくは「30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」という文言が、結果として「解雇予告」や「解雇予告手当」を支払えば従業員を解雇できるという認識に至っているようです。
解雇には客観的合理性と社会的相当性が必要
解雇については、民法と労働契約法に定めがあります。
ここでは民法の特別法に該当する「労働契約法」に注目する必要があります。
労働契約法第16条(解雇)
/引用:労働契約法
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法第16条には上記のように定められています。経営者の皆さんでも、少しは聞いたことのあるフレーズだと思います。「解雇権濫用法理」と呼ばれるものです。
これらのことを踏まえて頂くと…
この辺りがごっちゃになっていると、見出しや冒頭で述べたような勘違い(誤解)が生じてしまうのです。
ちなみに、お恥ずかしい話ですが、私も社労士試験の受験生時代の初めの頃は、この点(解雇予告と解雇の有効性の違い)を間違って理解していました。これらに関連した問題を解くにつれて、「あっ、そういうことか!」と腑に落ちた記憶があります。
不当解雇として訴えられることも

解雇では、解雇予告をした、解雇予告手当を支払ったということではなく、解雇が有効であったかどうかが問題となります。
先に説明したように労働契約法第16条に由来する解雇の客観的合理性・社会的相当性がなければ(解雇権濫用法理)解雇無効となり、労働者から「不当解雇」として訴えられる可能性もあります。
事の次第によっては、慰謝料や損害賠償と言ったお金の話だけでなく、解雇した従業員を再度雇うことになるとった事態も起こりえます。
そして、解雇することをより一層難しくしているのが、「どういった場合に不当解雇とならないかといった画一的なものはなく、それぞれ個別の事案ごとに判断される」ということです。こうしたら不当解雇にならない(解雇の有効性が立証される)といったことが言えないため、日本では採用に比べて解雇が非常に難しいのが現状です。
また、「能力が足りない」「注意しても言うことを聞かない」と言った簡単な理由で解雇ができないのには、日本の終身雇用という制度も影響しています。「一度雇った以上は定年まで雇い続ける、また雇う以上は従業員の教育(育てること)も会社の義務である」という考えが社会には存在しているからです。
判例などを踏まえると会社側には、十分な教育をしてもなお求める能力に及ばないことや、何度注意しても直らず一向に改善しないといったこと、配置転換をしてみるなど、会社側の指導履歴や従業員からの顛末書等といった材料を揃えて企業側の努力を見せつつ、客観的合理性と社会的相当性を証明する形になるのですが、それでもなお解雇権濫用法理に触れないと断言することは出来ないのです(個々の事案によるため)。
だからこそ、「はじめて従業員を雇うときに事前に押さえておきたい3つのポイント」で述べたように採用前、そして採用時に慎重な判断と選別、そして覚悟が求められるとも言えます。
労働者(従業員)からの退職(雇用契約の解約)
折角なので、使用者側ではなく労働者側(従業員)の視点でも少し触れておきます。
労働者は「2週間前に退職願いを出せば、会社を辞めることが出来る」という話を聞いたことはありませんか?
その根拠法が民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)となります。
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
/引用:民法より
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
この条文により、労働者が自己都合退職をする場合は、2週間前に言えば辞めることが出来るという訳です(厳密に言えば、月給制の場合は月の前半、年俸制の場合は三ヶ月前に解約の申入れが必要…といったことがあります)。
就業規則の規定に、退職の申入れは一ヶ月前、或いは三ヶ月前など法律(2週間前)より長い期間が定めれられている場合
就業規則に、「自己都合で退職する場合は、一ヶ月前(或いは三ヶ月前)に退職の申入れをすること」といったことが記載されている場合があります。
基本的には、就業規則の内容よりも法律が優先されると考えて下さい。
従って、一般的には退職の申入れ後、2週間経過すれば自動的に退職することができます。
しかし、使用者側(会社)としても、退職する労働者の代わりを探さなければなりませんし、これまでの業務内容の引き継ぎも必要です。
そういった会社側の事情も鑑みて、労使ともに円満な退職となるような配慮をすべきだと思います。
退職の申入れの期間が、1ヶ月前や3ヶ月前など法律より長く設定されているようであれば、それに従う形か、或いは出来る限り早く申し入れて会社に迷惑がかからない形で退職の手続きを進めるのが妥当でしょう。
まとめ
今回の記事では、
・使用者が、解雇するには客観的合理性と社会的相当性が必要
・一方で、労働者は2週間前に退職の申入れをすることで退職可能
・例え、就業規則の規定に2週間より長い期間(1ヶ月前や3ヶ月前)が定められていても、法律(2週間前)に定める申入れで退職することが可能(就業規則よりも法律が優先される)
といったことを説明しました。
経営者の皆さんが誤解されている、「30日前に解雇予告する、或いは30日分の解雇予告手当を支払えば従業員を解雇することが出来る」というのは間違いだということを覚えておいて下さい。解雇予告や解雇予告手当を支払ったとしても、解雇の有効性は成立しません。場合によっては、労働者から不当解雇として訴えられるおそれもあります。
また、労働者が重大な犯罪(暴行・傷害、横領など)を起こしたような場合を除き、(問題のない普通の)従業員を簡単に解雇することは大変難しいです。
だからこそ、採用時の面接や筆記なども工夫を凝らして、少しでも自社の希望に沿った労働者が雇えるような仕組みづくりも忘れないようにしましょう。